Cooling System
冷却水温度(以下、水温)は、サーキット走行をするほどの方なら関心が高いと思います。
多くの場合、上がりすぎる水温をどうやって下げようかと悩むことになります。
ただしこの水温、低ければいいというわけではなく適温というのが存在します。
例えばピストンは常温では円錐型になっており、適温になったときに初めて適正クリアランスになるように設計されています。
そのため冷間時はピストンの首振りが大きくなりますので、負荷の掛かる運転をすると磨耗を促進してしまうことになります。
もちろんピストンだけでなく、エンジン内部のクリアランスはすべて熱膨張を考慮して設けられていますので、冷間時は負荷を掛けないようゆっくり走るのが望ましいのは言うまでもありません(VTEC機構も水温がある程度上がるまでは作動しないようになっています)。
とは言え水温が上がり過ぎるとシリンダーヘッドの歪やガスケット抜けなどが起こってしまいますので、いかに適温を保てるかが重要です。
一部省略していますが、冷却系全般の図です。
サーモスタットがエンジン冷却水路出口(シリンダーヘッドとアッパーホースの間)にある出口制御型と、エンジン冷却水路入口(ロアホースとウォーターポンプの間)にある入口制御型がありますが、ホンダ車はほとんどが入口制御型ですのでそれに合わせています。
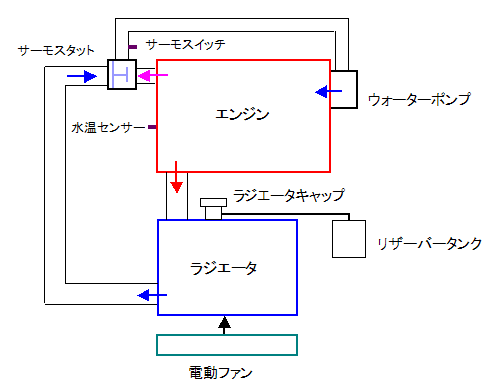
エンジンが始動すると、タイミングベルトによってウォーターポンプが回され冷却水が循環します。
ただし冷間時はサーモスタットの働き(低温では閉じており、高温で開く)により、ラジエータからの通路は閉じられているため冷却水はバイパス通路(図中の紫の矢印)を通って再びウォーターポンプへ入っていきます。
水温が上がっていくとサーモスタットが開き始め(これをサーモスタットの開弁温度と言います)、バイパス通路を塞ぎつつラジエータからの通路が開いていきます。
さらに水温が上昇してサーモスタットが完全に開くと(サーモスタットの全開温度と言います)バイパス通路は塞がれてしまい、冷却水はラジエータを通って循環することになります。
この状態で適温を保てればよいのですが、渋滞など走行風がない場合では水温が上昇しすぎることがあります。
そこでサーモスイッチが働くことになります。
このサーモスイッチは決められた温度になると導通し、それによって電動ファンが回り始めラジエータに風を当てて冷却します。
勘違いしがちなのですが、サーモスイッチが感知する温度はラジエータ通過後の水温であって、シリンダーヘッドの水温ではありません。つまり、ラジエータで冷却されたにもかかわらず高い温度であるときに働きます。
また、冷却水は温度が上がるにつれ膨張していきますが、その分だけ溢れ出てしまっては困りますのでラジエータキャップで蓋をしています。
ラジエータキャップは同時に冷却系の圧力を高く保ち、沸点を上げる役目も持っています(圧力が高いと沸点が上昇するため)。
しかしラジエータキャップが完全に密閉してしまうただの蓋では、冷却系内の圧力がどんどん高まっていきホースが破裂してしまいますので、決められた圧力を超えると加圧弁が開き、溢れた冷却水をリザーバータンクへと導いています。
エンジンが停止して水温が下がると今度は圧力が下がって負圧になりますので、キャップの負圧弁が開いてリザーバータンクから冷却水を吸い込むようになります。
ECUは冷間時のアイドルアップ、高温時の保護機能など水温によって細かい制御をしていますが、これはシリンダーヘッドに取り付けられている水温センサーの信号によって検出しています(ちなみにテクトムのCMX-100はこのセンサーが拾った値を利用していますので、ECUが把握している水温をそのまま表示できます。シリンダーヘッド水温を測定できますのでアッパーホースで測定するよりは誤差が少ないとされています)。
ラジエータ , Radiator

エンジンで発生した熱が冷却水に伝わったあと、その熱を大気中に放出するのがラジエータの役割です。
近くで観察してみるとよくわかりますが、細いチューブの中を冷却水が通り、そのチューブに接して多数のフィンが付いています。
このフィンの表面積が大きいほど多くの熱を捨てられるということになります。
社外品では材質が異なるものや層の数を増やしたものが見られます。
ただ、層の数が倍になっても能力が倍というわけではなく(前の層を通過した熱い空気が通るため)、望ましいのはラジエータの表面積を広くすることだと言われています。
ラジエータの性能は
放熱量Q=ρCL(Tin-Tout)
ρ:冷媒の比重 、 C:冷媒の比熱 、 L:循環量l/min
、 Tin:冷媒の入口温度 、 Tout:冷媒の出口温度
で表されます。
画像のPHASEラジエータは47,272cal、純正は23,533calとのことなので、どのくらい差があるのか簡単に計算してみました。
純正ラジエータで入口90℃、出口で85℃だったとすると、ρCLは
23,533=ρCL(90-85)
ρCL=4706.6
これを同一としてPHASEラジエータに交換した場合のToutは
47,272=4706.6(90-Tout)
Tout=79.9℃
となりました。
あくまで机上の計算ながら、5℃は温度を下げられることになります。
根本的に連続した高回転高負荷に対応するには、ラジエータの容量アップが最も望ましいと言えます。
サーモスタット , Thermostat
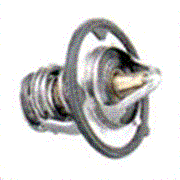
水温を応じて開閉し、オーバークールを避けるための装置です。
冷間時に冷却水がラジエータに回らないようにし、暖気時間を短縮しています。
水温によって開閉することにより、走行中に水温が下がりすぎたときも適温を保つようになっています。
ただし全開時にも通路面積が限られているため、サーキット走行時などでは若干抵抗になっています(ホンダ車用はありませんが、一部車種には開弁部の面積を広げた大流量タイプのサーモスタットもあります)。
社外品では開弁温度の低いものが販売されており(いわゆるローテンプサーモ)、これによって水温の上昇する速度をゆっくりにすることが出来ます。
ただし、あくまで早めにサーモが開くだけですから、水温の上昇する最大値を下げることは出来ません。
また、ある程度年式の経った車で街乗りでも水温が高くなってしまう場合は、このサーモスタットに問題があることがあります(完全に開弁しない)。
走行距離が伸びてきたら、交換しておくとよいでしょう。
ラジエータキャップ , Radiator-Cap
冷却系を加圧する役目を持っています。
気圧の低い山頂で100℃前に水が沸騰するのと同じ理由で、加圧することによって沸点を上昇させています。
最近の車では純正でも1.1kg/cm2となっており、これだけで沸点は120℃前後になっています。
社外品では開弁圧を高めたもの(いわゆるハイプレッシャーキャップ)がありますが、これは沸点を高めるだけですので水温を下げるわけではありません。
それよりも冷却系内により高い圧力(1.3k程度)を掛けることによって、ホースなどの負担を増している可能性もあります。
沸点を超えると冷却水は沸騰し、気泡を生じてしまいます(オーバーヒート)。
気体は液体のように熱を伝えませんので、さらに水温が上昇しエンジンに致命的なダメージを与えてしまう可能性があります。
ハイプレッシャーキャップはその沸点を高めるのですが、その恩恵を受ける前に他に異常が出そうにも思われます...
このキャップはスプリングを使用していますので、経たりが生じて開弁圧が低下してきます(0.1k/年と言われています)。
高価なものではありませんので、数年に1度は交換しておくとよいでしょう。
サーモスイッチ・冷却ファン , Thermo-Switch・Cooling-Fan
走行風が期待できない渋滞時などにラジエータに風を当てる冷却ファンですが、これはサーモスイッチによってON/OFFされています。
ユーロRではサーモスイッチの作動温度は95℃になっていますが、若干高めのように感じられます。
そのために設定温度を制御できるVFC-MAXやより低い温度で動作するサーモスイッチなどが販売されています。
冷却ファンが早めに回ることにより、サーキットで待機しているときなど水温を低く保つことができます。
ただし、速度の出るサーキットでは走行風が充分に当たるためにファンの動作は関係ないばかりか、走行風の抜けが悪くなるためにかえって抵抗になることもあるようです。
クーラント , Coolant
冷媒として使用するには水がベストとされていますが、凍結防止や防錆・潤滑のためにLLC(ロングライフクーラント)が用いられるのが普通で、最近ではより比熱の高い(熱が伝わりやすい)クーラントも販売されています。
クーラントも劣化して防錆能力が落ちてきますので、定期的に交換する方が望ましいのですが、最近のホンダ車では10年間交換不要というクーラントが入っています。
交換時には成分が異なっていますので、混用しない方が無難です。
日常ではクーラントの量に注意しておきましょう。
上に書いている通り、温間時はリザーバータンク内の液量は増え、冷間時には減りますので点検は冷間時に行います。
ユーロRはどの車もクーラントが減る傾向にあるようなので、特に注意しておきましょう。
冷間時にLOレベル近くになっていたら、ディーラーで補充してもらうようにします(通常のLLCなら水を補充しても構いません)。
結局のところ、サーキット走行で水温を安定させるには容量の大きいラジエータに交換するのが手っ取り早いと言えます。
サーモスタットも全開で走行風も十分に当たる状態なのに水温が上がってしまうのであれば、ラジエータの容量をアップするしかありません。
しかしローテンプサーモやサーモスイッチでも水温の上昇速度を緩やかにすることができますので、インターバルを取りながらの走行なら効果があります。
また暖房用のヒーターコアも一種のラジエータのようなものですから、走行中にヒーターをONにしておくと若干の水温低下が期待できます。
どの場合でもラジエータに風が多く当たるようにすることが重要で、ラジエータに虫が張り付いていたり小石が挟まっていたら、きれいに取り除いてフィンの曲がりも修正して掃除しておきましょう(高圧洗浄ではフィンが曲がってしまうので注意が必要です)。
またサーキット走行時に限れば、ナンバープレートは走行風がラジエータに当たる障害でしかありませんので、外しておくとよいでしょう。


